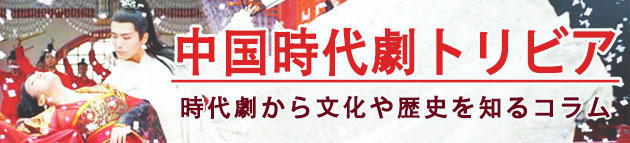
物語を語るパフォーマー「説話人」とは?|中国時代劇トリビア#135
“人気作家”と“新任の長官”として再会したちょっぴりワケありな2人が、小説とそっくりな事件の謎を探っていくハラハラドキドキのミステリーロマンス時代劇「鹿苑記~僕の生意気な彼女~」。今回はこのドラマに登場するキーワードについて、探ってみたいと思います!
「説話人」とは?

「鹿苑記~僕の生意気な彼女~」© Chaoneng Film (Beijing) Co., Ltd
「鹿苑記~僕の生意気な彼女~」のヒロイン・鹿南一(ホアン・イー演)は金州で人気の作家・説話人。第一話の冒頭で鹿南一は、自身が執筆した小説の物語を観客に向けて堂々と語り上げます。
観衆の前で物語を語るパフォーマンスは、評書などとも呼ばれる中国伝統の口承芸術で、宋代から流行したそう。琵琶や三弦、また、刷板とよばれる鳴り物をならしながら物語を語り、語り部が自分の出身地のお国言葉を使って様々な物語を語って聞かせることが、一つの方言文化ともされていたそうです。
起源は中国の北方地方伝統の評書文化だったとも言われているそう。評書は書(文字)に対して批評を語るものと、演技や演奏、物語を語るものなどがあり、その中から物語を口頭で語る芸術ジャンルが独立し、清代初期にはそのスタイルが確立されていったのだとか。
一方で、唐代には評書の表現スタイルと発展の仕方がよく似た「説話」という民間芸術が登場。この語り物の台本として、話本が生まれていきます。「説話」は、伝統的な故事を語るというよりは、観衆により楽しんでもらう要素が重要視されたようです。いずれのパフォーマンスも、ストーリーテラーは物語を演じる俳優であると同時に物語を生み出す作家でもあり、鹿南一が作家で説話人という肩書になるのも、こうした背景があったことが予想されます。
ここで少し、評書がどのようにパフォーマンスされたのかも見ていきましょう。清朝末期から中華民国初期にかけての評書は、テーブルの後ろに1人で座って行われ、扇子、テーブルを叩く醒木(鹿南一も劇中で使っていましたね!)などの小道具と、長衫などの衣装を着用していました。やがて20世紀中ごろになると、テーブルを始めとした小道具は使われなくなり、立ったままのパフォーマンスが行われるようになり、衣装もあまり固定されなくなったとか。また、一人で物語の筋を語ったり、登場人物を真似たり、物事について批評を入れたりするなど、さまざまな芸術的な表現で、歴史的および現代的な物語を再現しながら話すのが基本とされていましたが、2人でかけあうものや、複数人で演じるなど、スタイルの変化も生まれていったそう。1970年代後半の中国の改革開放以降、電子メディアや北京語の普及の影響で、一部の方言の物語文化は徐々に衰退し、消滅の危機に瀕したこと時代がありつつも、依然として活力を保っているとも言われているそうです。
百度「評書」
発売・販売元:エスピーオー 提供:エスピーオー/BS12 トゥエルビ
https://www.spoinc.jp/official/rokuenki/

Text:島田亜希子
ライター。中華圏を中心としたドラマ・映画に関して執筆する他、中文翻訳も時々担当。Cinem@rtにて「中国時代劇トリビア」「中国エンタメニュース」を連載中。『中国時代劇で学ぶ中国の歴史』(キネマ旬報社)『見るべき中国時代劇ドラマ』(ぴあ株式会社)『中国ドラマ・時代劇・スターがよくわかる』(コスミック出版)などにも執筆しています。
中国時代劇を見て感じるちょっとした不思議や疑問を解説します。



記事の更新情報を
Twitter、Facebookでお届け!
Twitter
Facebook